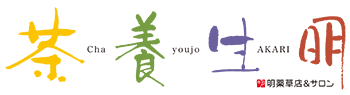≪和名≫ 桑、くわ、桑白皮、そうはくひ、桑葉、そうよう、桑椹(実)、そうじん
≪生薬名≫ ソウハクヒ
≪科目≫ クワ科 クワ属
≪分布≫ 中国原産の落葉高木で北海道から九州の日本各地と朝鮮半島から中国大陸の産地に分布する落葉高木植物ですが昔から絹糸になるマユを作る解雇の餌として栽培されてきました。
≪出典≫ 神農本草経
《成分》DNJ(1-デオキシノジリマイシン)が含まれており、DNJは桑にしか含まれない成分で、これは砂糖やデンプンを小腸内でαーグルコシダーゼと言う糖分解酵素が分泌されるのでブドウ糖に変えて吸収させるのを阻害させる。
《くわを煎じて服用した場合》
糖尿病の予防と改善、血糖値上昇の抑制などに効果
≪採取時期≫
根…桑の根を掘り出して水洗いをし、生のうちに外側の皮とコルク層を取り除いて日干しします 鎮咳、去痰、利尿、咳止、気管支炎
葉…7月から8月の夏季に厚みのある葉を摘み取ってから日干しします。美容と健康維持
枝…秋から冬に枝を切り取ってから日干しします。 美容と健康維持
実…食する場合は黒紫になってから食し、果樹酒にする場合は赤い状態の時に採取し、水洗いをしてから漬け込みます。美容と健康維持
クワ・よもやま話
桑の葉は古代中国では「神仙茶」と呼ばれ、色々な病気予防に服用されていました。
中国では東方海上の島国に「扶桑」と呼ばれる巨木(神木)があると言われていました。日本を別名で「扶桑国」といい昔は日本に桑の巨木があったのかもしれません。
古代日本(卑弥呼の時代)について書かれた「魏志倭人伝」に桑を蚕に与えて糸を紡いでいたとの記事が見られ、弥生時代や卑弥呼の時代には桑を利用していたことが分かります。時代が下がって鎌倉時代に栄西禅師が書いた茶書の「喫茶養生記」によると、「飲水病」(糖尿病)に桑を服用すると数日で効果がみられる。とあります。
これは桑に含まれる成分のDNJ(1-デオキシノジリマイシン)が砂糖やデンプンを小腸内でαグルコシターゼという糖分解酵素がブドウ糖に変えて小腸からの吸収を阻害します。